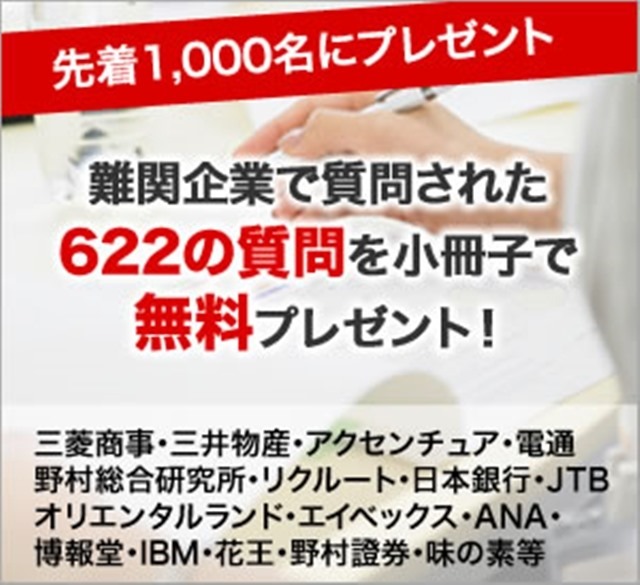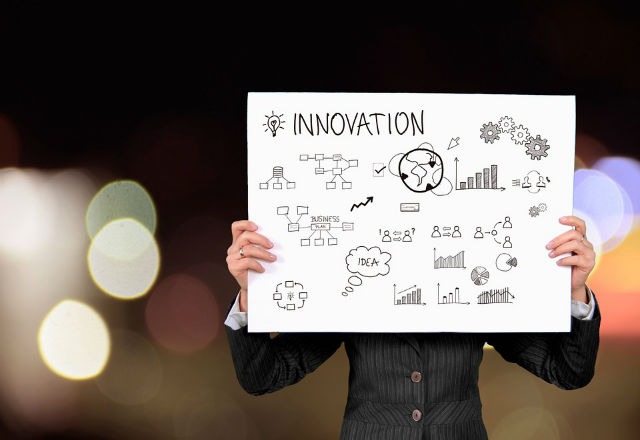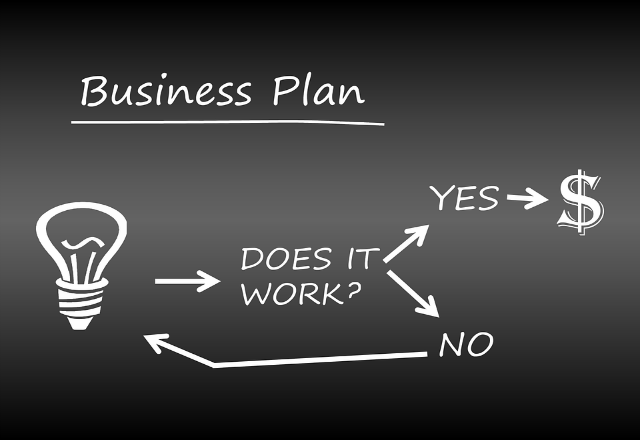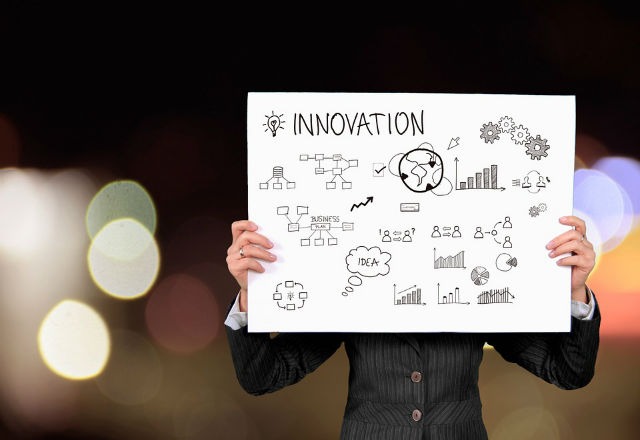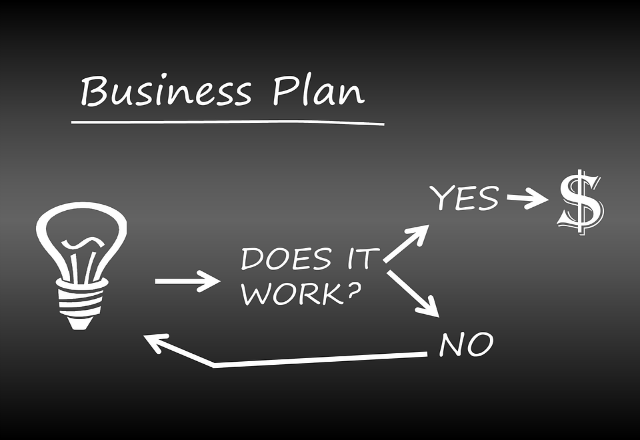気になる年収・有休取得の話〜あの企業が1位!〜退職までにいくらもらえるの?
企業を選ぶとき、福利厚生もチェックしていますか?
2016.09.21
ざっくり言うと
- 平均年収ランキング
- 生涯賃金ランキング
- 有給休暇取得率ランキング
はじめに
企業選びにおける就活生の最初の判断基準になるのが"給料や休みの有無"ではないでしょうか。
どうせ仕事をするなら給料は多くもらえた方がいい・しっかりと休みをもらえる企業で働きたいと考えるのは当然ですし、同じ仕事なら給料の高い企業を選ぶのも理にかなっています。
そこで今回は "平均年収・生涯賃金・有給休暇取得率"について特集していきます!
平均年収ランキングTOP30
いわゆる年収とは・・・
▶︎毎月の給料に、夏と冬の年2回の賞与を加えた数字。
ボーナスが多ければ、その年の年収も大きくなる。では、実際にどんな企業でどれくらいの年収を貰っているのだろうか。
☆ランキングの見るべきポイント☆
①従業員の平均年齢
▶︎このランキングは純粋な平均年収の高い順にならべてある。
そのため同じ年収ならば平均年齢の若い企業の方が平均年収は高いことになる。
②従業員数
▶︎従業員数が少ない企業ほど平均年収が高くなる傾向にある。
新卒採用を行っていない場合やバックオフィス(事務員)などの人たちが少ないために平均年収が上 振れする傾向にある。また、社長や管理職の人たちの年収が影響しやすいため。
以上より平均年齢が若く、従業員数の多い企業に関しては、総合職で入社した場合この数字よりも高い額をもらえる可能性がある。
※純粋持ち株会社は、グループ企業の管理を担う特性上、経験豊富な従業員が集まる場合が多い。そのため、事業子会社に比べて数値は上振れる傾向にある(社名の横に「(純)」とあるのが、該当企業)。また、主要事業子会社が有価証券報告書を提出している場合、より実態に即したランキングとなるよう、子会社のデータを採用した(社名の横に「(子)」とあるのが、当該企業)出典 http://toyokeizai.net/articles/-/71024(東洋経済ONLINE)
上位を見るとおなじみの日本を代表する企業が並んでいますね。
しかし、その中にあまり見慣れない、GCAサヴィアン・日本M&AセンターというM&A(合併・買収)関連の企業が名を連ねています。近年はM&Aの需要が急速に増えており、また莫大なお金が動く一方で、M&Aをできる人は日本にはまだそれほどいないので、生産性がかなり高いが故にこのような結果になっていると考えられます。
生涯賃金ランキングTOP30
生涯賃金とは・・・
▶︎会社に新卒で入社して定年まで働いたときに取得できる総額
☆ランキングの見るべきポイント☆
平均年収と同様に平均年齢と従業員数は見るべきポイントである。
加えて "生涯給料2億円"は一つの目安とされる。その5割増しの3億円超は約180社と全体の約5%程度で、同2倍の4億円以上となると25社となり、同1%以下に絞られる。
有給休暇取得率ランキングTOP30
有給休暇とは・・・
労働者の休暇日のうち、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日のことである。
▶︎厚生労働省「平成27年就労条件総合調査」によると、日本の民間企業の平成27年(2014年)の有給休暇取得率は"47.6% "と50%を下回る状態が続いている。思うように有休を取れる人ばかりではないのが現状だ。
ただ、そうした中でも取得率の高い会社はある。今回は毎年恒例の有給休暇取得率ランキングを作成。有給休暇取得の先進企業をその取り組み内容とあわせてご紹介する。
☆ランキングの見るべきポイント☆
①取得率が50%を超えているかどうか
▶︎日本の民間企業の取得率が50%弱なのでこれを超えている超えていないかが一つの指標になる。
有給休暇は1年間でおよそ20日与えられていることが多いので、年間で約10日の休みが得られるのが平均的である。
②取得率が増加傾向にあるかどうか
▶︎近年は政府が有給休暇の取得率をあげようとしている方針もあり、日系の大手企業では社会的責任が大きいために取得率が上がっている
傾向にあるが、しっかりとその傾向にそっているのかどうかで今後のその企業の方針がわかる。
表を見ると製造業やメーカーが圧倒的に多いですね。
これは日本の強みが製造業であることから日本を代表する企業が多いので結果として社会的責任を果たすためにこのような数字になっていると考えられます。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
企業選びをする際にどこから決めていいかわからない人は、入りとして上記のような観点から興味を持つこともいいかもしれません。
しかし、"志望動機などはこれだけではいけません"。興味を持ったら企業研究やOB訪問を行いより深いものにしていきましょう!
OB訪問メールやり方
OB訪問質問集
OB訪問レポートまとめ
企業研究
業界研究